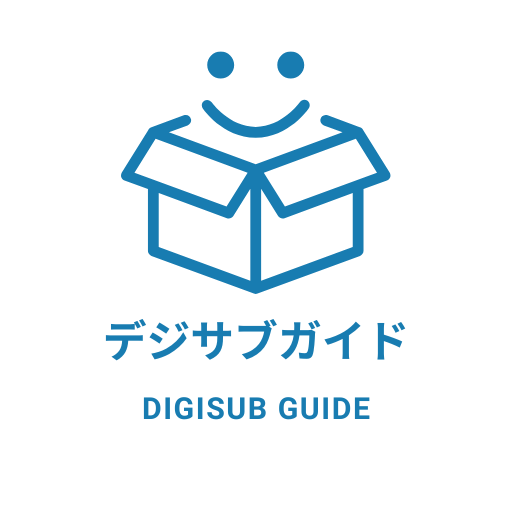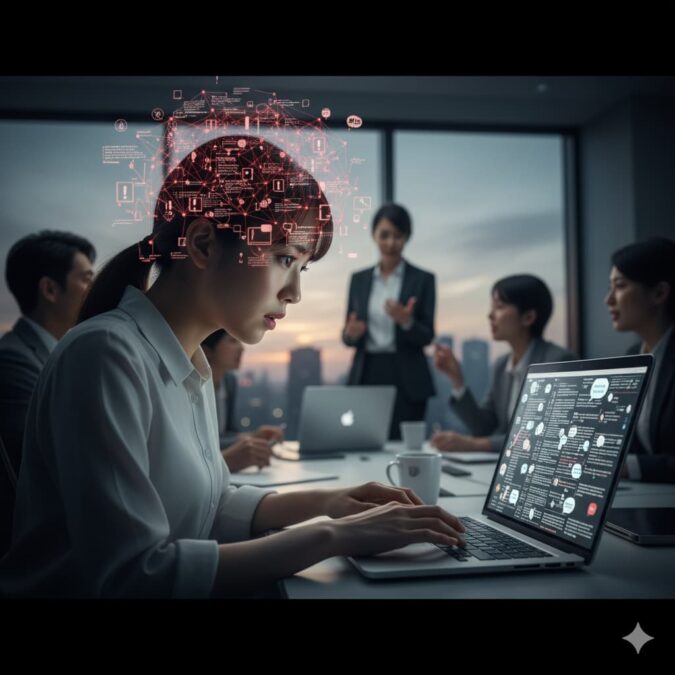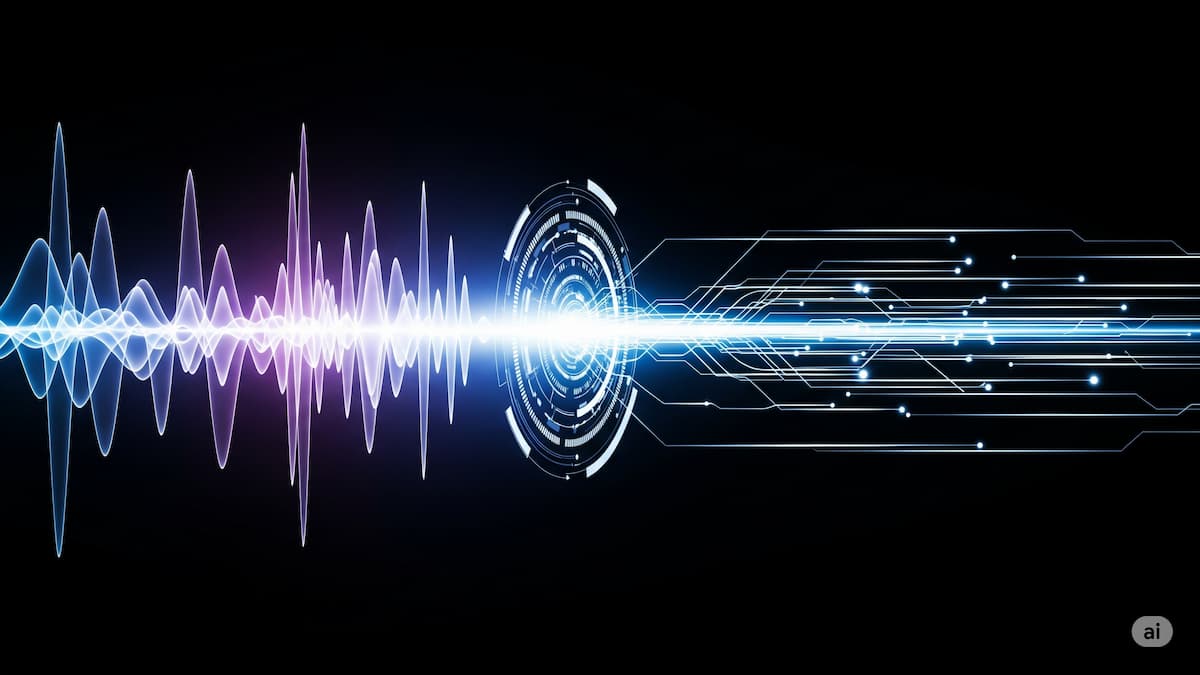会議の議事録、聞きながら書くのって本当に大変ですよね。「議事録、聞きながら書けない…」と悩んでいる人は多いと思います。話を聞きながらメモを取ろうとしても、議論のスピードに追いつかない。重要な要点を押さえようとしても、タイピングが間に合わず、結局「文字起こし」のような作業になってしまう。これって、個人の能力や練習法が足りないだけなのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。特にADHDの特性があるわけではなくても、人間の脳は「聞くこと」と「書くこと」という2つの複雑なタスクを同時に行うようには、そもそも設計されていないんです。脳の仕組み上、それは極めて難しい作業なんですね。議事録作成のコツとして略語を使ったり、必死で要約を意識したりする方法もありますが、正直、限界がありますよね。
最近、私はこの「議事録、聞きながら書けない」という積年の悩みを、根本から解決してくれる便利なAI議事録アプリの存在を知りました。この記事では、なぜ私たちがあれほど議事録作成に苦労していたのか、その脳科学的な理由と、NottaやPlaud NoteといったAIツールが、その苦労をどう解消してくれるのかを、詳しく紹介していきます。
この記事のポイント
- なぜ「聞きながら書けない」のか、その原因
- 議事録作成でメモが追いつかない理由
- AI議事録ツールがおすすめな理由
- NottaやPlaud NoteなどのおすすめAIツール
「議事録が聞きながら書けない」は当然だった
会議中に「聞きながら書く」ことが、なぜこんなにも難しいのでしょうか。必死でタイピング練習をしたり、メモ術の本を読んだりしても、なかなか上達しない…。実は、それはあなたの能力不足や努力不足ではなく、人間の脳の仕組みに根差した、ごく自然な現象だったんです。このセクションでは、その根本的な理由と、多くの人が無意識に陥っている「書けない」落とし穴について、少し深く見ていきます。
議事録作成でメモが追いつかない
会議が始まると、まるで言葉の洪水です。次から次へと発言が飛び交い、「あ、今の重要かも」と思ってキーボードに手をかけた瞬間に、議論はもう次の話題に移っている…。これは、議事録担当者なら誰もが経験する「あるある」ですよね。
それもそのはず、人間の会話スピードは、私たちが思っている以上に速いのです。プロのタイピストであっても、会話を一言一句リアルタイムで書き取るのは至難の業。ましてや、私たちは会議中、単にタイピングしているだけではありません。「話を聞く」「内容を理解する」「情報の重要度を判断する」「要点をまとめる」「タイピングする」という、5つもの複雑な作業を同時に(マルチタスクで)処理しようとしています。
人間の脳には、情報を一時的に保持し処理するための「ワーキングメモリ」という機能がありますが、その容量には限界があります。(出典:治療と職業生活の両立におけるストレスマネジメントに関する研究(厚生労働省))複数の高度なタスクを同時に行おうとすると、脳はすぐにキャパシティオーバーを起こしてしまいます。これが「認知的過負荷(コグニティブ・オーバーロード)」と呼ばれる状態です。結果として、メモが議論に追いつかない、重要な部分を聞き逃す、といった事態が必然的に発生するのです。
完璧主義は「追いつかない」最大の原因
この「追いつかない」状況をさらに悪化させるのが、「一言一句すべて書こう」とする完璧主義です。議事録は「完全な文字起こし(トランスクリプト)」ではありません。後で読み返したときに「何が決まったか」「次に何をすべきか」が分かれば良いのです。この目的意識を明確にし、「全部書く」という強迫観念を捨てることが、まず重要です。
議事録が書けない本当の理由
「メモが追いつかない」という速度の問題以外にも、「書けない」理由はいくつか潜んでいます。そして、最大の原因は、実は会議が始まる前にある「準備不足」です。
会議の「目的」や「ゴール」、そして「アジェンダ(議題)」を事前にまったく把握していない状態で参加したと想像してみてください。議論の中で「何が重要で、何が単なる雑談か」を判断する基準(フィルター)を、あなたは持っていないことになります。
この準備不足は、以下のような負の連鎖を生み出します。
議事録作成・負の連鎖
- アジェンダを把握していないため、議論のゴールが分からない。
- ゴールが分からないため、どの発言が決定事項に結びつく「重要なポイント」か区別できない。
- 区別ができないため、聞き逃しを恐れるあまり「安全策」として、すべての発言を書き留めようとする。
- その結果、H3-1で触れた「完璧主義の罠」に陥り、必然的に議論のスピードについていけなくなる。
多くの人はこの結果だけを見て「自分のタイピングが遅いからだ」と誤って判断しがちですが、真の問題は「準備不足によって、書く必要のないことまで書こうとしている」ことにあるのです。
また、これに加えて、会議中に文書の体裁を整えたり、誤字脱字を修正したりと、リアルタイムで「きれいに整理(清書)」しながら書こうとするのも失敗の原因です。これは、「聞く」「書く」に加えて「編集する」という第3のタスクを無理やり詰め込んでいるに他なりません。
ADHD特性と議事録作成の困難
ここまで説明したように、「聞く」と「書く」の同時処理は、脳の仕組み上、誰にとっても難しい作業です。中でも、ADHD(注意欠如・多動症)の特性がある方にとっては、これが一般の人以上に大きな困難となって立ちはだかることがあります。
ADHDの特性の一つに、注意を一点に持続させたり、複数の情報(この場合は「音声」と「思考」と「タイピング」)を同時に処理したりすることが、脳の特性上難しい、という側面があります。会議中、一つの発言に深く集中している間に別の情報が入ってきて思考が中断されたり、逆にメモを取ることに意識が向くと、直前の発言内容が頭から抜け落ちてしまったり…。
大切なのは「特性」を理解し、「仕組み」で解決すること
重要なのは、これが個人の「能力」や「やる気」の問題ではなく、脳の「特性」によるものだということです。そのため、「頑張って集中する」「気合で乗り切る」といった根性論では、消耗してしまうだけです。
最も現実的で効果的な解決策は、その特性を前提として、「同時処理を根性で頑張る」のではなく、「同時処理そのものを避ける」ための仕組みやツール(まさにAI議事録ツールです)を積極的に活用することです。
※本セクションは、健康に関する一般的な情報提供を目的としています。ADHDの特性や診断については、個人の判断に頼らず、必ず専門の医療機関にご相談ください。最終的な判断は、医師や専門家の指導のもとで行うようにしてください。
議事録作成のコツを掴む
AIツールは強力ですが、それに頼る前に、まず手動でもできる「コツ」を知っておくと、議事録作成のスキルは格段に上がります。AIが生成した要約を修正する際にも、この「コツ」が役立ちます。
準備段階のコツ:会議の「前」が9割
1. アジェンダの確認とテンプレートの用意 これが全ての基本であり、最も重要です。会議が始まる前に、必ず「なぜこの会議が開かれるのか(目的)」と「この会議で何を決めるのか(ゴール)」を正確に把握します。そして、事前に共有されたアジェンダ(議題)を元に、「議事録テンプレート」を作成します。
最強の議事録テンプレート例
- 日時: 2025年11月2日(日) 14:00〜15:00
- 場所: Web会議 (Zoom URL: http://...)
- 出席者: 〇〇様、△△様、□□(自分)
- 議題:
- 新機能Aの進捗確認
- プロモーション予算の件
- 次回のスケジュール
- 決定事項: (ここに書く!)
- 議論内容:
- (議題1について)
- (議題2について)
- (議題3について)
- 懸案事項 / TO DO: (誰が・何を・いつまでに)
会議が始まったら、白紙のドキュメントを開くのではなく、このテンプレートの空欄を埋めていく作業に集中するだけです。これだけで、脳の負荷は劇的に下がります。
会議中のコツ:すべてを「書かない」勇気
2. 「何を書くか」ではなく「何を書かないか」を決める 完璧主義を捨てます。議事録の目的は、主に以下の3点に集約されます。
- 情報共有: 欠席者や関係者に、何が起こったかを伝える。
- 認識のすり合わせ: 決定事項を明文化し、「言った・言わない」を防ぐ。
- タスク管理: 「誰が何をすべきか」を明確にし、次の行動を促す。
この目的を達成するためには、議論の9割を占める雑談や、結論に至らなかった思考プロセス、冗長な言い回しは「ノイズ」です。議事録作成者の仕事は、このノイズを積極的に「書かない」と判断し、本質だけをフィルタリングすることです。
3. 必須要素に集中する テクニック2を実践するために、メモを取る対象を、以下の「5つの必須要素」に限定します。これら以外の情報は、基本的に無視する覚悟が重要です。
- 決定事項: 「A案を採用する」「予算は50万円とする」といった、会議の結論。
- 理由: なぜその決定に至ったのか、という簡潔な根拠。(例:コストメリットが大きいため)
- タスク (TO DO): 「誰が(担当者)」「何を」「いつまでに」行うかという具体的なアクションプラン。
- 数字・固有名詞: 日付、予算、人員数、製品名など、客観的で間違えてはならない事実情報。
- 発言者: 重要な意見や決定、タスクの割り当てに関連する人物の名前。(※必須ではないが、あると後で役立つ)
議事録作成の練習法とは
こうした「コツ」を掴んでも、すぐに実践するのは難しいものです。もし「書く力」そのものを長期的に鍛えたいなら、地道な練習ももちろん効果があります。
要約力のトレーニング(AI時代の最重要スキル)
AIツールがどれだけ進化しても、人間の「要約力」は必要です。むしろ、AIが生成した膨大な文字起こしテキストの「本質」を見抜き、文脈を理解した上で簡潔にまとめる力こそ、AI時代に最も重要になるスキルだと私は考えています。
要約力とは、「書き手の意見や解釈を入れず」、元の文章の「エッセンス」だけを抽出し、「自分の言葉で簡潔にまとめる」技術です。
- 読書と要約: 本や新聞記事を読み、各章やセクションの要点を「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識して数行でまとめる習慣をつけます。
- 「一言で言うと」訓練: 自分が伝えたいことや読んだ記事を「一言で言うと何か?」と自問し、中心的なメッセージを1文で定義する訓練をします。これは物事の「核」を見抜く練習になります。
- アクティブ・リスニング: 日常会話の中で、相手の発言を聞きながら「つまり、〇〇ということですね」と頭の中(あるいは実際に)で要約し、確認する癖をつけます。
タイピング速度の向上(正確性重視で)
AIツールが主流になっても、AIが生成したテキストの修正作業や、チャットでのコミュニケーションなど、基礎的なタイピング速度は依然として重要です。タイピングが速ければ、それだけ思考のスピードを妨げません。
ただし、タイピング上達の鍵は、スピード(WPM: Words Per Minute)よりも「正確性(Accuracy)」を優先することです。どれだけ速く打てても、誤字脱字だらけでは、修正作業でかえって時間がかかります。
まずはキーボードを見ずに打つ「ホームポジション」を徹底的にマスターすること。速度は、正確性の副産物として自然に上がっていきます。
「議事録が聞きながら書けない」悩みの終焉
これまで紹介した「コツ」や「練習」は、確かに有効です。私自身もこれらのテクニックを駆使して、なんとか議事録作成を乗り切ってきました。しかし、忙しいビジネスパーソンにとって、毎回完璧な準備をしたり、練習の時間を確保したりする余裕がないことも多いですよね。
ここからは、「議事録 聞きながら 書けない」という根本的な、そして積年の悩みを、テクノロジーの力で一掃する方法、つまりAIツールの本格的な活用について、詳しく紹介していきます。これは、もはや「あれば便利」なものではなく、「必須のビジネススキル」になりつつあると私は感じています。
要点を押さえるメモ術
「議事録作成のコツを掴む」でも触れましたが、AIツールを導入したからといって、人間が何も考えなくて良くなるわけではありません。AIツールを使う場合でも、人間が「要点」を意識することは、依然として非常に重要です。
なぜなら、AIは現時点では「会議の空気感」や「発言の裏にあるニュアンス」、「どれが本当に重要な決定事項なのか」を100%正確に判断することはできないからです。AIは完璧な文字起こしはしてくれますが、そのテキストの「重み」までは汲み取れないことがあります。
そこでおすすめなのが、AIと人間のハイブリッドなメモ術です。
会議中、AIに録音・文字起こしを任せつつも、自分は「議論の大きな流れ」を追うことに集中します。そして、「あ、今タスクが発生したな」「これが今日の結論だな」という「要点」の瞬間だけを手元のメモ(あるいはAIツールのコメント機能やブックマーク機能)に書き留めておきます。例えば、「★決定:A案採用(理由:コスト)」「→田中さん:クライアント資料作成(金曜まで)」といった具合です。
この「タグ付け」のような簡単な作業をしておくだけで、会議後にAIが生成した膨大な文字起こしデータ(1時間の会議でも数万文字になります)を確認する際、「どこを重点的に修正・確認すべきか」が一目瞭然になります。AIにすべてを任せるのではなく、「AIの長所(網羅的な記録)」と「人間の長所(文脈の理解と重要度の判断)」を組み合わせる。これが、現代における最強のメモ術です。
略語や記号で効率化する
前述の「要点を押さえるメモ術」を実践する際、キーボードを打つ量をいかに減らすかが、議論への集中力を保つ鍵となります。そこで有効なのが、H3-4でも軽く触れた「略語」や「記号」の活用です。
AIツール(Nottaなど)の多くには、よく使う単語やフレーズを登録しておける「辞書登録」機能がありますが、それと同時に、自分だけの「メモ用記号」を決めておくと、思考を止めずに素早く記録できます。
これは、複雑な日本語の「意味」を処理するのではなく、単純な「記号」として入力する行為であり、脳のワーキングメモリを節約するのに非常に効果的です。
| 記号 | 意味 (Meaning) | 使用例 (Example) |
|---|---|---|
| ★ (または *) | 重要事項 / 決定事項 | ★ A案を採用 |
| → (または ->) | タスク / 次のアクション | → 田中さん:クライアント連絡 (10/25まで) |
| ? (または Q) | 要確認事項 / 疑問点 | ? 納期は変更可能か、A社に確認 |
| ! (または C) | 注意点 / リスク | ! 機密情報のため、取り扱い注意 |
| ↑ / ↓ | 増加 / 減少 | 売上 ↑ (前年比10%) / コスト ↓ (5%削減) |
| ○ / □ | 完了 / 未完了タスク | ○ 企画書提出 (山田) / □ 戦略立案 (佐藤) |
これらの記号は、後でAIの文字起こしテキストを検索する際の「目印(アンカー)」としても非常に優秀です。例えば、テキスト全体から「→」を検索するだけで、会議中に発生したタスク(TO DO)を漏れなくピックアップできます。
まずは録音で議論に集中する
AI議事録ツールを導入する最大のメリットは、突き詰めればこの一点に尽きます。「会議を録音する」。たったこれだけのアクションが、議事録作成者のマインドセットを根本から変えます。
なぜなら、「すべてをリアルタイムで書き残さなければならない」という、あの強迫観念から完全に解放されるからです。録音データという「絶対的なセーフティネット」があるという安心感は、想像以上に大きいものです。
これにより、私たちはメモ取りに必死になる必要がなくなり、本来の目的である「会議の議論そのもの」に100%集中できるようになります。相手の目を見て話を聞き、議論の意図を汲み取り、時には自分から積極的に質問や提案をすることも可能になります。これは、単なる「筆記者」ではなく、「会議の参加者」として非常に重要な変化です。
聞き逃した部分や、発言のニュアンスが曖昧だった部分は、後から何度でも確認できるため、議事録の正確性も飛躍的に向上します。
録音の絶対的ルール:事前の許可
ただし、この「録音」には絶対的なルールがあります。それは、会議の開始前に、必ず全参加者から「録音の許可」を得ることです。
無断での録音は、重大なマナー違反であるだけでなく、信頼関係を著しく損ねる行為です。場合によっては、法的な問題に発展する可能性もゼロではありません。
会議の冒頭で、次のように目的を明確にして許可を求めましょう。
「皆様、本日の議論と決定事項を正確に議事録に残すため、この会議を録音させていただいてもよろしいでしょうか? 録音データは、議事録作成の目的以外には一切使用いたしません。」
このように、「正確性の担保」や「タスク漏れの防止」といった、参加者全員の利益(メリット)になる点を強調するのがコツです。誠実に伝えれば、断られることはほとんどないはずです。
AIが要約と文字起こしを自動化
録音するだけなら、スマートフォンの標準ボイスレコーダーアプリでも十分です。しかし、AI議事録ツールの真価は、その録音データを活用した「自動化」と「効率化」にあります。
高精度な「文字起こし」
近年のAIの進化はすさまじく、日本語の音声認識精度は、数年前とは比べ物にならないレベルに達しています。多少の専門用語や業界用語(AIツールによっては辞書登録も可能)も、高精度に認識してくれます。
これにより、私たちが1時間の会議内容をゼロから手動でタイピングする(専門家でも平均4時間、素人ならそれ以上かかるとも言われます)という、最も時間のかかる、単純かつ苦痛な作業がほぼゼロになります。これは革命的と言っても過言ではありません。
もちろん、AIの精度を最大限に引き出すには、録音の「音質(インプット)」も重要です。高品質なマイクを使う、静かな環境を選ぶ、発言者が明瞭に話す、といった基本的な配慮で、AIの精度はさらに向上します。
AIによる「自動要約」
そして、文字起こし以上に強力なのが「要約」機能です。AIが、数万文字にも及ぶ膨大な文字起こしデータ全体を解析し、「重要なキーワード」を抽出し、「決定事項」や「タスク」らしき部分をハイライトし、全体の要約案を作成してくれます。
正直なところ、2025年現在、AIの自動要約が「完璧」かというと、そうではありません。時には文脈を読み間違えたり、重要でない部分をピックアップしたりすることもあります。
しかし、重要なのはマインドセットです。「ゼロから要約を考える」のと、「AIが作った80点の要約案を、人間が100点に修正する」のとでは、作業負荷は雲泥の差です。AIが作った「たたき台」があるだけで、議事録作成の心理的ハードルは劇的に下がります。
AIの登場により、議事録作成者の役割は、単なる「タイピスト(筆記者)」から、AIの出力をレビューし、文脈を整える「エディター(編集者)」へと明確に進化しました。
AI議事録アプリ(NottaやPlaud Note)
では、具体的にどのAIツールを選べばよいのでしょうか。AI議事録ツール市場はまさに戦国時代ですが、デジサブガイドとしても、この分野は特に注目しています。ここでは、私の視点から、用途別におすすめの代表的なツールをいくつか紹介します。
高機能・高精度な万能型「Notta(ノッタ)」
Nottaは、現在のAI議事録ツールの代表格と言える存在です。まず、音声認識の精度が非常に高い。リアルタイムでの文字起こしはもちろん、Zoom、Microsoft Teams、Google Meetといった主要なWeb会議ツールとの連携もスムーズです。
Web会議にNottaのボットを自動で参加させておけば、自分が出席できない会議の議事録(文字起こしと要約)も後から確認できます。また、英語や中国語など多言語対応も強力なので、グローバルな会議がある方にも最適です。「議事録作成を本格的に効率化したい」というチームや個人に、まず最初におすすめしたいオールインワン・ツールです。無料プランもありますが、本格的に活用するなら有料プランが前提になるでしょう。
こちらもCHECK
-

-
Nottaの3日間無料トライアルの始め方・解約方法を解説
AI文字起こしツール「Notta」の高精度な機能を試してみたいけれど、いきなり有料プランに登録するのは少し不安ですよね。そんな時に便利なのが、Nottaの3日間無料トライアルです。 しかし、実際に利用 ...
続きを見る
革新的な録音デバイス「Plaud Note(プラウドノート)」
Plaud Noteは、Nottaのようなソフトウェア(アプリ)とは少し毛色が違います。これは「AIボイスレコーダー」という専用のハードウェア(ガジェット)です。クレジットカードほどの薄いカード型デバイスで録音すると、その音声が専用アプリに転送され、即座にChatGPT(GPT-4)と連携し、高精度な文字起こしと要約を自動生成してくれます。
Plaud Noteの強みは「対面会議」と「手軽さ」
Plaud Noteの最大の強みは、「オフラインの対面会議」や「とっさのメモ」にあります。Web会議ならPCで録音も簡単ですが、対面の打ち合わせで、いきなりテーブルにスマホを置くと、相手が話しづらさを感じることがありますよね。Plaud Noteなら、胸ポケットや手帳に入れたまま、相手に威圧感を与えることなく自然に録音が可能です(もちろん、録音の許可は必要ですよ!)。
ガジェット好きとしては、この「スマートに録音できる」という体験自体に非常に魅力を感じます。オンライン会議がメインならNotta、対面会議や外出先での「サッと録音」が多いならPlaud Note、というのが私の使い分けイメージです。
こちらもCHECK
-

-
PLAUD NOTEレビュー|AI要約機能と使い方・評判を徹底解説
「PLAUD NOTE レビュー」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、AIを搭載したこの最新デバイスに大きな関心を寄せていることでしょう。 PLAUD NOTEは単なる AIボイスレコーダー で ...
続きを見る
議事録が聞きながら書けない悩みの解決する総括
ここまで見てきたように、「議事録、聞きながら書けない」という悩みは、もはや根性論や個人のスキル不足で乗り越える時代ではありません。人間の脳の特性上、「聞く」と「書く」という高度な知的作業の同時処理は難しい、という事実をまず受け入れましょう。
その上で、テクノロジー(AI)の力を最大限に借りて、その「同時処理」を意図的に回避するプロセスを構築すること。これが、現代のビジネスパーソンにとって最もスマートで、効果的な解決策です。
結論:AI時代の議事録作成プロセス
- 準備: アジェンダ(議題)を確認し、会議のゴール(決定事項)を頭に入れておく。
- 会議中: 参加者の許可を得て、AIツール(NottaやPlaud Noteなど)で録音を開始する。人間は「聞きながら書く」ことを放棄し、議論に100%集中する。要点(決定事項やタスク)の瞬間だけ、記号(★や→)などでメモ(タグ付け)する。
- 会議後: AIが自動生成した「文字起こし」と「要約案」を受け取る。
- 仕上げ: AIの要約案を「たたき台」として、自分のメモ(タグ)を参考にしながら、ニュアンスを修正し、タスクを確定させ、議事録として関係者に共有する。
AIに「書く」という苦痛な作業を任せることで、あなたは「聞きながら書けない」という長年の悩みから解放されます。そして、そこで生まれた時間と脳のリソースを、より本質的な「議論への参加」や「意思決定の推進」、そして「次のアクションの実行」に使うことができるようになるはずです。