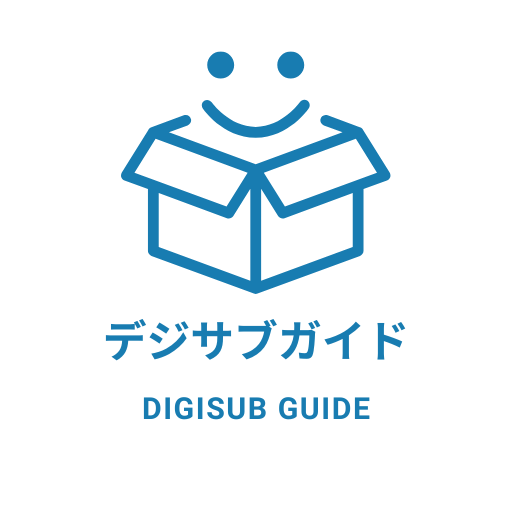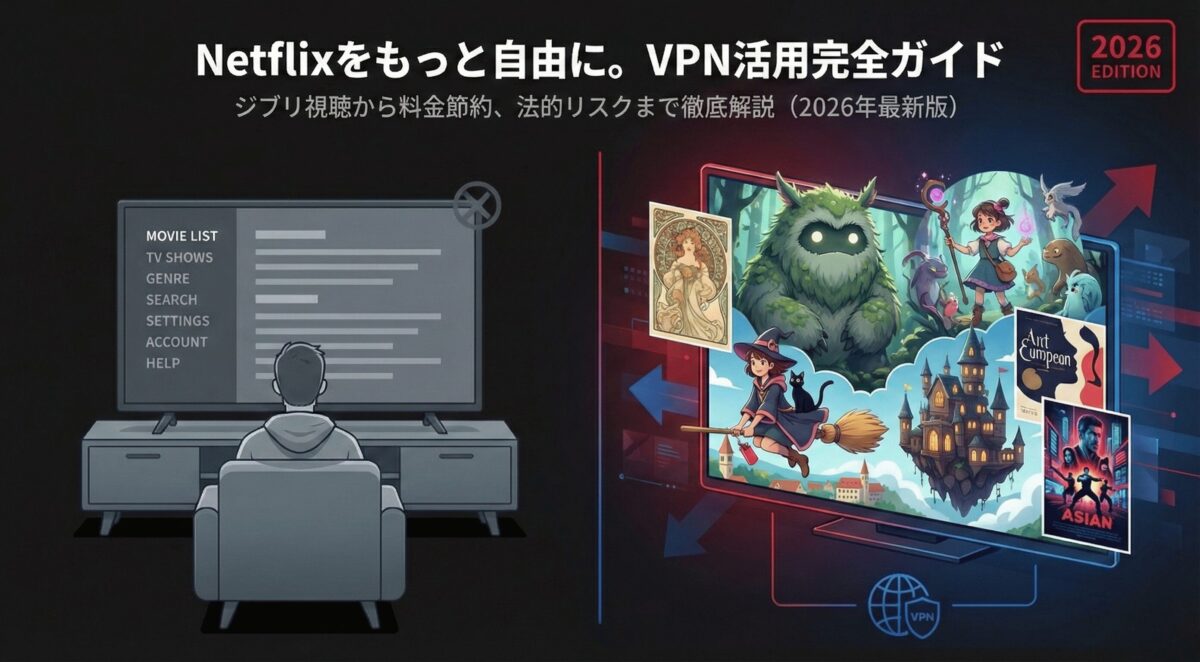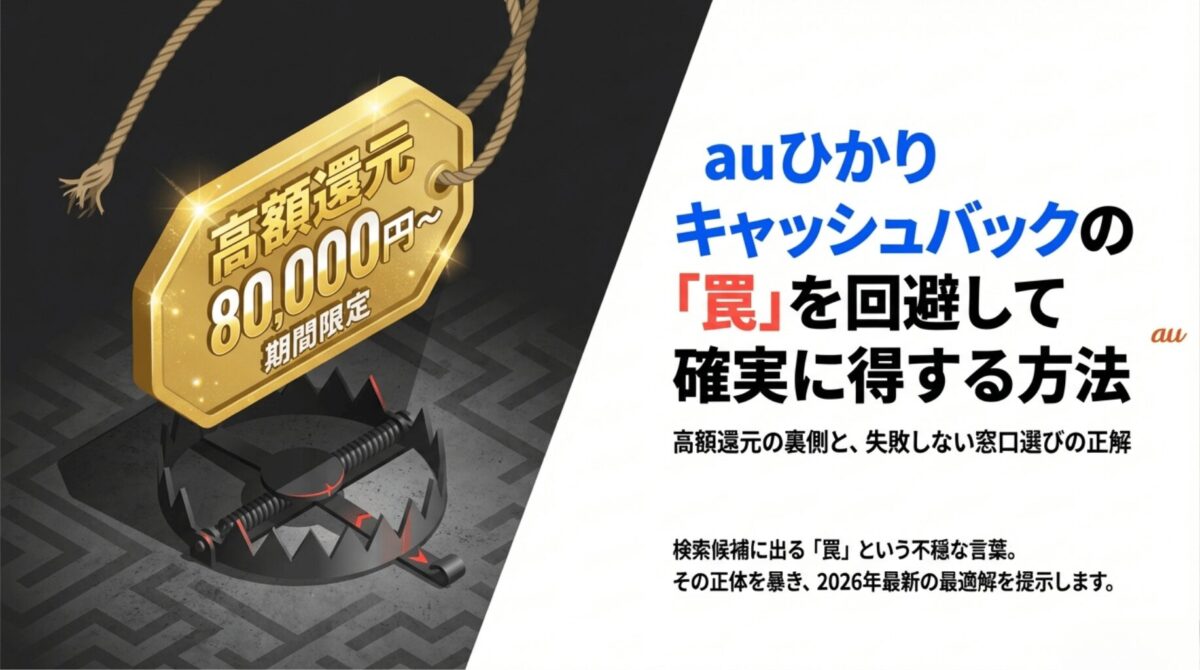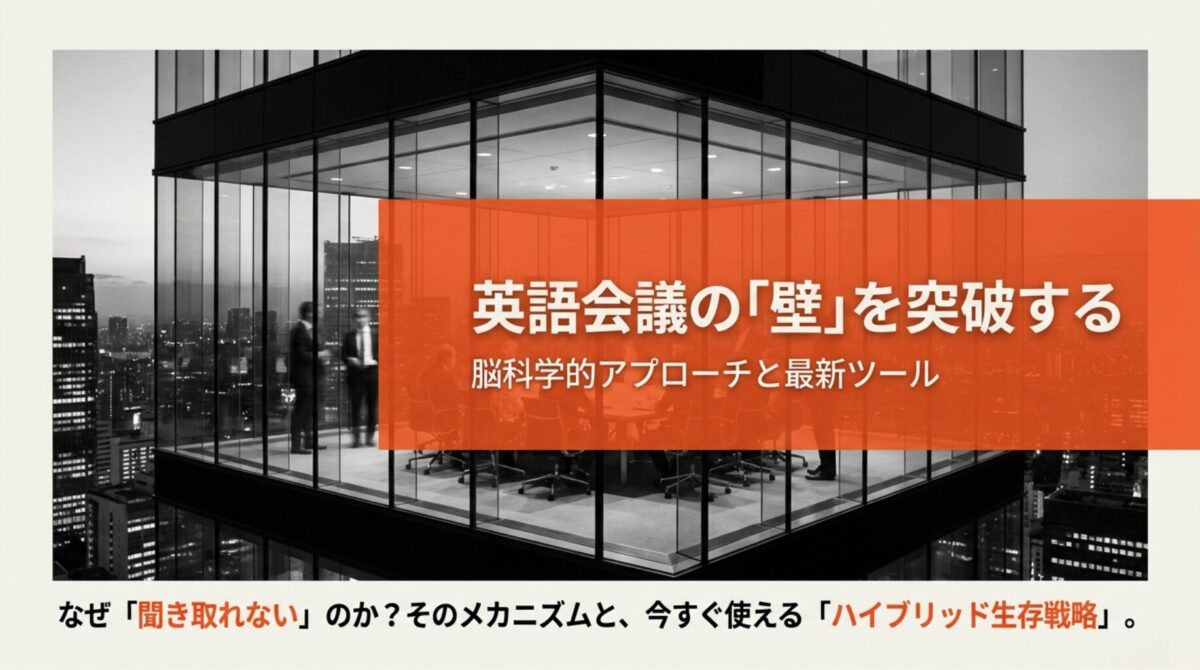「NotionとGoodnotesの使い分け、どうすればいいの?」多くの人がこの問いに頭を悩ませています。多機能なNotionは、便利なNotionテンプレートを駆使したまとめノート作成や、Notion文献管理テンプレートによる情報整理に長けていますが、Notionの手書き機能には限界があるのが実情です。一方で、手書きノートをデジタルで管理したいなら、Goodnotesは非常に強力な選択肢となります。しかし、Goodnotesはマークダウンに対応しておらず、テキストベースの整理は得意ではありません。このため、GoodnotesとEvernoteでどっちが良いか迷う方もいらっしゃいます。この記事では、基本的なNotionのノートの取り方から、進化したNotionとGoodnotes6の連携方法、そして手書きノートをNotionで一元管理する具体的なテクニックまで、あなたのノート環境を劇的に改善するための最適な使い分け戦略を徹底的に解説します。
この記事のポイント
- NotionとGoodnotesの基本的な役割と違い
- それぞれのアプリに最適なノートの取り方
- 両アプリを連携させる具体的なテクニッ
- あなたに合った使い分けモデルの見つけ方
NotionとGoodnotes使い分けの基本戦略
- Notionテンプレートでノートを効率化
- Notionでまとめノートを作成する利点
- 基本的なNotionのノートの取り方とは
- Notion文献管理テンプレートの活用法
- Notionの手書き機能はどこまで使えるか
- GoodnotesとEvernoteはどっちを選ぶ?
Notionテンプレートでノートを効率化
Notionを使いこなす上で、最も強力な機能の一つが「テンプレート」です。テンプレートを利用することで、議事録、タスク管理、読書記録など、用途に応じたノートの型を瞬時に作成できます。これにより、毎回ゼロから構成を考える手間が省け、情報入力に集中できるため、作業効率が飛躍的に向上します。
例えば、講義ノート用のテンプレートをあらかじめ作成しておけば、授業が始まる前にワンクリックで準備が完了します。日付や講義名、キーワードといった項目を設けておくことで、後から見返した際の検索性も高まるでしょう。このように、テンプレートは単なる時短ツールではなく、情報を構造化し、再利用性を高めるための重要な基盤となるのです。
テンプレート活用のポイント
Notionには公式テンプレートだけでなく、世界中のユーザーが作成した多種多様なテンプレートが存在します。自身の学習スタイルや目的に合ったテンプレートを探し、それを自分流にカスタマイズしていくことが、Notionを最大限に活用する鍵と言えます。
私であれば、まずはシンプルなToDoリストやコーネル式ノート術のテンプレートから試してみて、徐々に自分に必要なプロパティ(タグや日付など)を追加していく方法をおすすめします。最初から完璧を目指さず、使いながら育てていく感覚が大切です。
Notionでまとめノートを作成する利点
学習した内容を記憶に定着させる上で、「まとめノート」の作成は非常に有効な手段です。特にNotionは、その優れた機能性からまとめノート作成に最適なツールと言えます。最大の利点は、テキスト、画像、動画、Webリンク、さらにはデータベースまで、あらゆる情報を一つのページに集約できる点にあります。
紙のノートや他のアプリではバラバラになりがちな情報を、Notionでは関連性を保ったまま一元管理できます。例えば、ある疾患について学習する場合、講義ノート、関連論文のPDF、参考となるWebサイトのリンク、そして症例データベースを全て同じページにまとめられるのです。これにより、知識が点ではなく線、さらには面として繋がり、深い理解を促進します。
特に便利なのが「トグルリスト」機能です。質問と答え、あるいは重要なキーワードとその説明をトグル内に記述しておくことで、ページをすっきりと保ちながら、能動的な復習(アクティブリコール)が可能になります。これは記憶の定着に非常に効果的です。
また、階層構造を無制限に作れるため、大項目から小項目へと掘り下げていくような、体系的なノート構築も得意です。このように、情報の集約性と構造化のしやすさが、Notionでまとめノートを作成する大きなメリットと言えるでしょう。
基本的なNotionのノートの取り方とは
Notionでのノート作成は、白紙のページに文字を打ち込むだけではありません。その真価は、「ブロック」という概念を理解することから始まります。Notionでは、文章の段落、見出し、画像、リストなど、ページ上の全ての要素が個別の「ブロック」として扱われます。このブロックをドラッグ&ドロップで自由自在に移動させたり、種類を変更したりできるのが最大の特徴です。
基本的なノートの取り方の流れは以下の通りです。
- ページを作成する: まずは新しいページを作成し、タイトルをつけます。
- テキストを入力する: 普通のメモアプリのように、まずは思いついたことを書き出していきます。
- ブロックを変換する: 書き出したテキストを、見出しや箇条書き、チェックリストなどに変換します。「/(スラッシュ)」コマンドを使うと、様々なブロックを素早く呼び出せるので非常に便利です。
- ページを構造化する: 関連するブロックをまとめたり、カラム機能で2列や3列にレイアウトしたりして、情報を整理します。
「/(スラッシュ)コマンド」を使いこなそう
「/」を入力すると、挿入可能なブロックのリストが表示されます。例えば、「/h2」と入力すればH2見出しに、「/todo」と入力すればToDoリストに即座に変換可能です。このショートカットを覚えるだけで、ノート作成のスピードが格段に上がります。
このように、Notionのノートの取り方は「まず書き出す→後から構造化する」という流れを意識するとスムーズに進みます。最初から完璧な構成を目指す必要はなく、思考の流れを止めずに情報を記録し、後から自由に編集できる柔軟性がNotionの魅力です。
Notion文献管理テンプレートの活用法
医学部生や研究者にとって、膨大な数の論文を効率的に管理することは重要な課題です。Notionは、データベース機能を用いることで、非常に高機能な文献管理システムを構築できます。「Notion 文献管理テンプレート」を利用すれば、このシステムを誰でも簡単に導入することが可能です。
テンプレートの基本的な構成は、論文1本を1つのアイテム(ページ)として管理するデータベースです。各アイテムには、以下のような情報(プロパティ)を設定できます。
- 論文タイトル: 論文の表題
- 著者: 論文の著者名
- 出版年: 論文が発表された年
- 雑誌名: 掲載された雑誌や学会
- ステータス: 「未読」「精読中」「読了」などの進捗
- キーワード: 論文のテーマを示すタグ
- URL/DOI: 論文へ直接アクセスできるリンク
- PDF: 論文のPDFファイルそのもの
これらのプロパティを設定しておくことで、「特定のキーワードを持つ論文だけを表示する」「未読の論文を優先度順に並べる」といった柔軟なフィルタリングや並べ替えが可能になります。さらに、各論文のページ内には、読んだ際のメモや要約、疑問点などを自由に書き込めるため、情報が散逸することもありません。
注意点:引用リストの自動生成はできない
MendeleyやZoteroといった専門の文献管理ツールとは異なり、Notion単体では論文執筆時の引用リスト(参考文献リスト)を特定のフォーマットで自動生成する機能はありません。この点を理解した上で、あくまで個人の学習や情報整理のハブとして活用するのが良いでしょう。
Notionの手書き機能はどこまで使えるか
結論から言うと、現在のNotionには、Goodnotesのような本格的な手書き機能は搭載されていません。そのため、Apple Pencilなどを使って自由に文字や図を書きたい、というニーズにNotion単体で応えるのは難しいのが現状です。
一応、ExcalidrawやMiroといった外部のドローイングツールを連携させて、Notionのページ内に手書きの図を埋め込むことは可能です。しかし、これはあくまで画像として埋め込まれるものであり、GoodnotesのようにPDFの上に直接書き込んだり、手書き文字を後から検索したりすることはできません。
Notionは手書き入力の代替にはならない
「PCとiPadを行き来したくない」「パソコン1台で学習を完結させたい」という理由でNotionを選ぶ場合でも、手書きがメインの学習スタイルの方には不便を感じる可能性が高いです。手書きの自由度を重視する場合は、後述するGoodnotesとの連携を検討するのが現実的な解決策となります。
このように言うとNotionの弱点ばかりが目立つかもしれませんが、これはツールの特性の違いです。Notionは「構造化された情報のストック」に特化しており、手書きのような「自由な発想の記録」は他のツールに役割を分担させる、という考え方が重要になります。
GoodnotesとEvernoteはどっちを選ぶ?
手書きノートアプリを検討する際、Goodnotesと並んで候補に挙がるのがEvernoteです。どちらも優れたアプリですが、得意なことが異なるため、自身の目的によって選ぶべきアプリは変わってきます。ここでは両者の違いを比較し、どちらを選ぶべきかの指針を示します。
一言で言えば、「手書き体験」を最優先するならGoodnotes、「情報収集と整理」を重視するならEvernoteが適しています。
| 機能 | Goodnotes | Evernote |
|---|---|---|
| 手書き機能 | ◎(非常にスムーズで多彩なペン) | △(機能は限定的で、手書きは画像扱い) |
| PDFへの書き込み | ◎(直接インポートして書き込める) | ○(有料プランで可能) |
| テキスト入力 | ○(キーボード入力も可能) | ◎(高機能なエディタを搭載) |
| 情報整理(タグ・フォルダ) | ○(フォルダ、アウトライン機能) | ◎(強力なタグ付け、ノートブック機能) |
| Webクリップ | △(限定的) | ◎(非常に高機能) |
| マルチデバイス対応 | △(Apple製品中心、Windows/Androidも対応開始) | ◎(ほぼ全てのプラットフォームに対応) |
私であれば、講義資料(PDF)に直接メモを取りたい、解剖図に書き込みをしたいといった、「手書き」が学習の中心になる場合は迷わずGoodnotesを選びます。一方で、Web記事やメールなど、様々な形式の情報をとにかく一箇所に集めたいという「スクラップブック」的な使い方であれば、Evernoteの強力なクリップ機能が活きるでしょう。
今回のテーマであるNotionとの使い分けを考える上では、手書き機能に特化したGoodnotesの方が、役割分担が明確で連携させやすいと言えます。
実践的なNotionとGoodnotes使い分け術
- 手書きノートをNotionに集約する方法
- 効果的なNotionとGoodnotesの連携
- NotionとGoodnotes6の新機能と相性
- Goodnotesはマークダウンに対応してる?
- 最適なNotionとGoodnotesの使い分け
手書きノートをNotionに集約する方法
Goodnotesの強みである「手書きの自由度」と、Notionの強みである「情報の構造化と一元管理」。この二つを組み合わせることで、理想的な学習環境を構築できます。ここでは、Goodnotesで作成した手書きノートをNotionに集約する具体的な方法を解説します。
最もシンプルで一般的な方法は、GoodnotesのノートをPDF形式でエクスポートし、それをNotionのページにアップロード(添付)する方法です。これにより、Notionのデータベース内で、他の情報と関連付けて手書きノートを管理できます。
手順の具体例:
- Goodnotesでノートを作成: 講義ノートやアイデアスケッチなどを自由に書き込みます。
- PDFとして書き出す: Goodnotesの共有機能から「書き出す」を選択し、フォーマットで「PDF」を選びます。
- Notionにアップロード: Notionの該当ページを開き、「/file」コマンドでファイルブロックを呼び出し、先ほど書き出したPDFを選択してアップロードします。
OCR機能の活用
Goodnotesで作成したPDFは、手書き文字をテキストとして認識するOCR(光学的文字認識)処理が施されている場合があります。このPDFをNotionにアップロードすると、Notionの検索機能で手書きノートの内容も検索対象になる可能性があり、非常に便利です。
この方法により、「普段のメモは手書きが快適なGoodnotesで、長期的な保管や体系的な整理はNotionで」という、両アプリの長所を活かしたワークフローが完成します。
効果的なNotionとGoodnotesの連携
前述のPDFエクスポート以外にも、NotionとGoodnotesを連携させる効果的な方法がいくつか存在します。目的に応じてこれらの方法を使い分けることで、よりシームレスな情報管理が可能になります。
一つは、Goodnotesの「リンク共有機能」を活用する方法です。Goodnotes 5.5以降では、ノートブックへの共有リンクを生成できるようになりました。このリンクをNotionのページに貼り付けることで、NotionからワンクリックでGoodnotesの該当ノートをWebブラウザやアプリで開くことができます。
この方法のメリットは、PDFをエクスポートする手間が不要な点と、Goodnotes側でノートを更新すれば、Notionのリンク先も常に最新の状態に保たれる点です。言ってしまえば、Notionを「目次」や「ハブ」として使い、手書きノートの実体はGoodnotesに残しておく、という運用が可能になります。
もう一つの方法は、iPadのマルチタスク機能(Split ViewやSlide Over)を駆使する方法です。画面の半分にNotion、もう半分にGoodnotesを表示させて作業します。例えば、Notionで学習計画や論文リストを確認しながら、Goodnotesで実際の学習やメモ書きを進めることができます。さらに、Goodnotesで書き込んだ図やスクリーンショットを、そのままNotionのページにドラッグ&ドロップで貼り付けることもでき、非常に効率的です。
これらの連携テクニックをマスターすれば、二つのアプリがまるで一つのアプリのように連携し、生産性を大きく向上させることができるでしょう。
NotionとGoodnotes6の新機能と相性
近年、両アプリはAI機能の搭載など目覚ましい進化を遂げており、連携の可能性もさらに広がっています。特に最新版であるGoodnotes6の新機能は、Notionとの連携において大きなメリットをもたらします。
Goodnotes6の目玉機能の一つが、強化されたAIによる手書き認識です。例えば、手書きで書いた文章のスペルミスをAIが検知して修正候補を提示してくれたり、走り書きした文字を瞬時にきれいなテキストに変換したりできます。これにより、手書きの気軽さとテキストの再利用性を両立しやすくなりました。Goodnotesで手書きしたメモをAIでテキスト化し、それをコピーしてNotionのまとめノートに貼り付ける、といったワークフローが非常にスムーズになります。
数式変換機能も強力
また、手書きの数式を認識して、画像やLaTeX形式のテキストに変換する機能も搭載されました。これは理系の学生や研究者にとって非常に強力な機能です。計算過程はGoodnotesで自由に手書きし、清書した数式だけをNotionに貼り付けてレポートを作成する、といった使い方が考えられます。
Notion側のAI機能との連携
一方、NotionにもAI機能が搭載されており、取り込んだ文章の要約や翻訳、ブレインストーミングの補助などが可能です。Goodnotesで書き留めたアイデアの断片をNotionに集約し、Notion AIを使ってそれらのアイデアを構造化したり、文章を生成させたりする、といった相乗効果も期待できるでしょう。
このように、両アプリの進化、特にAI機能の充実は、これまでの連携をさらに深化させ、より高度な知的生産活動をサポートしてくれるものとなります。
Goodnotesはマークダウンに対応してる?
結論として、Goodnotesは現在、マークダウン記法に正式には対応していません。マークダウンとは、「#」で見出し、「*」で箇条書きといったように、簡単な記号を使って文章を構造化する記述方法です。Notionをはじめ多くのテキストエディタでサポートされています。
Goodnotesはあくまで「デジタルの紙」としての手書き体験を重視して開発されているため、テキストの構造化を目的としたマークダウンとは思想が異なります。キーボードでテキストを入力することは可能ですが、それはノート内の一要素という位置づけであり、マークダウンによる効率的なテキスト編集機能は備わっていません。
マークダウンを使いたい場合の代替案
もし、手書きとマークダウンの両方を使いたい場合、Goodnotesで手書きの図やアイデアを作成し、それを画像としてエクスポートします。そして、UlyssesやBear、あるいはNotionといったマークダウン対応のアプリにその画像を貼り付け、テキスト部分はマークダウンで記述するという方法が考えられます。
この事実は、GoodnotesとNotionの役割分担を考える上で非常に重要です。文章の構造化や長文の執筆、整形はNotion(あるいは他のマークダウンエディタ)で行い、Goodnotesはあくまで手書きに特化して使う、という明確な線引きが、両アプリを快適に使いこなすための鍵となります。
最適なNotionとGoodnotesの使い分け
これまで解説してきた内容を踏まえ、あなたにとって最適なNotionとGoodnotesの使い分けモデルを提案します。これはあくまで一例であり、最終的にはご自身の学習スタイルや目的に合わせてカスタマイズすることが最も重要です。
おすすめの使い分けモデル:ハイブリッド型
このモデルは、両アプリの長所を最大限に活かすことを目的としています。
- 情報の入り口と自由な発想:Goodnotes
講義中のメモ、思いついたアイデアのスケッチ、PDF資料への書き込みなど、スピーディな入力や自由な表現が求められる場面ではGoodnotesを活用します。
- 情報の集約と構造化、長期保管:Notion
Goodnotesで作成したノートや、Web記事、動画、タスクなど、あらゆる情報をNotionのデータベースに集約します。Notionでは情報を体系的に整理し、後から容易に検索・再利用できる「第二の脳」として機能させます。
具体的には、「今日の学習」というタスクをNotionで管理し、そのタスクページ内にGoodnotesで作成したノートのリンクを貼る、といった運用が考えられます。こうすることで、Notionで学習計画の全体像を把握しつつ、具体的な学習内容はGoodnotesで快適に行う、という理想的な分業が実現します。
まとめ:最終的な使い分け
最終的に、どちらのツールをメインにするか、あるいはどのように連携させるかはあなたの好み次第です。この記事を参考に、まずは無料プランやトライアル期間を活用して両方のアプリを実際に試してみてください。自分の思考プロセスや学習スタイルにしっくりくる方法を見つけることが、デジタルノートを使いこなす上での最大の秘訣と言えるでしょう。
- 情報集約とデータベース化はNotionが最適
- 自由な手書きやPDF注釈はGoodnotesの独壇場
- Notionは構造的なノート作成に向いている
- Goodnotesは流動的な思考の記録に適している
- 役割を明確に分けることが使い分けの基本
- 情報の入り口はGoodnotes、整理と保管はNotionというモデルが有効
- PDFに書き込むならGoodnotesが第一選択肢となる
- 長期的な知識ベース構築にはNotionが不可欠
- Notionのテンプレート機能でノート作成を効率化できる
- Goodnotesのリンク共有でNotionとの連携がスムーズになる
- iPadのマルチタスク機能で両アプリを同時に使うと便利
- Goodnotes6のAI機能はテキスト化を助け連携を強化する
- 手書き文字の検索性を重視するならOCR機能が鍵となる
- マークダウン記法はNotion、手書きはGoodnotesと割り切る
- 最終的には自身のスタイルに合わせてカスタマイズすることが最も重要